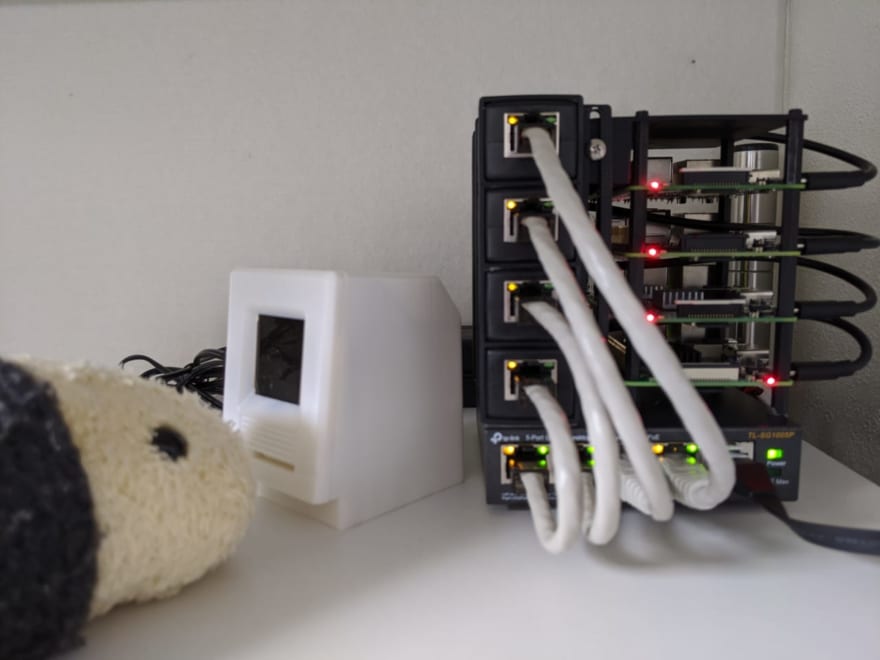明けましておめでとうございます。とうとう東京オリンピックイヤーですね。
と、どうでも良い前置きは置いといて、今回は「PoEスプリッターとRaspberry Piでミニサーバールーム構築」を行います。
ミニサーバールーム構築と書きましたが、ただPoEをRaspberry Piで使いたかっただけになります。。。(えっ。
※ちなみにPoEとは、Power Over Ethernet の略で、1本のLANケーブルでデータと一緒に電力も送っちゃえる規格になります。
というのも、自宅では用途別に複数のRaspberry Piをサーバーとして運用しております。
具体的には、
・外からのアクセスをプロキシーするリバースプロキシーサーバー(NGINX)
・家族で使うWebアプリケーションを動かすアプリケーションサーバー(Tomcat)
・コード管理用のGitサーバー(GitBucket)
・WebアプリケーションやGitサーバーで利用するデータベースサーバー(MariaDB)
の計4台が稼働しております。(このブログサーバーはちゃんと有料のサービスを契約して運用していますよ。)
データベースサーバーは、Raspberry Pi 3Bでそれ以外は、Raspberry Pi 2です。
最近のトレンドでは、dockerなるものを利用して仮想化したりするのでしょうが、知識もないのでRaspberry Piを物理的に複数台用意して運用をしています。
そもそも大した処理をしてるわけでもないし、物理的に壊れても影響が少ない点が良いです。
Raspberry Pi自体も最新機種でなければ、フリマなどで安く手に入るのでお手軽です。
ただ、複数台になるとそれなりに配線がかさばるので、PoEスプリッターを利用してミニサーバールーム風なものを構築しようとした次第です。
Raspberry Pi用の専用PoEハットも発売はされているのですが、対応しているRaspberry Piが3B+以降なのと、そもそも PoEハット自体が高価なので見送りました。
今回は、以下の PoEスプリッターを利用しました。

 AliExpress.com Product – IEEE 802.3af Micro USB Active PoE Splitter Power Over Ethernet 48V To 5V 2.4A for Tablet Dropcam or Raspberry Pi
AliExpress.com Product – IEEE 802.3af Micro USB Active PoE Splitter Power Over Ethernet 48V To 5V 2.4A for Tablet Dropcam or Raspberry Pi
一つ800円程度なのでお手軽です。100Mbpsまでしたか対応していませんが、最近までのRaspberry Pi自体のLANがそもそも100Mbpsなので問題ないです。
※一応値段が倍になりますが1Gbpsのスプリッターも売っています。
次に電力の共有側は、PoE対応のTP-Link スイッチングハブ ギガ 5ポート PoEハブを購入しました。
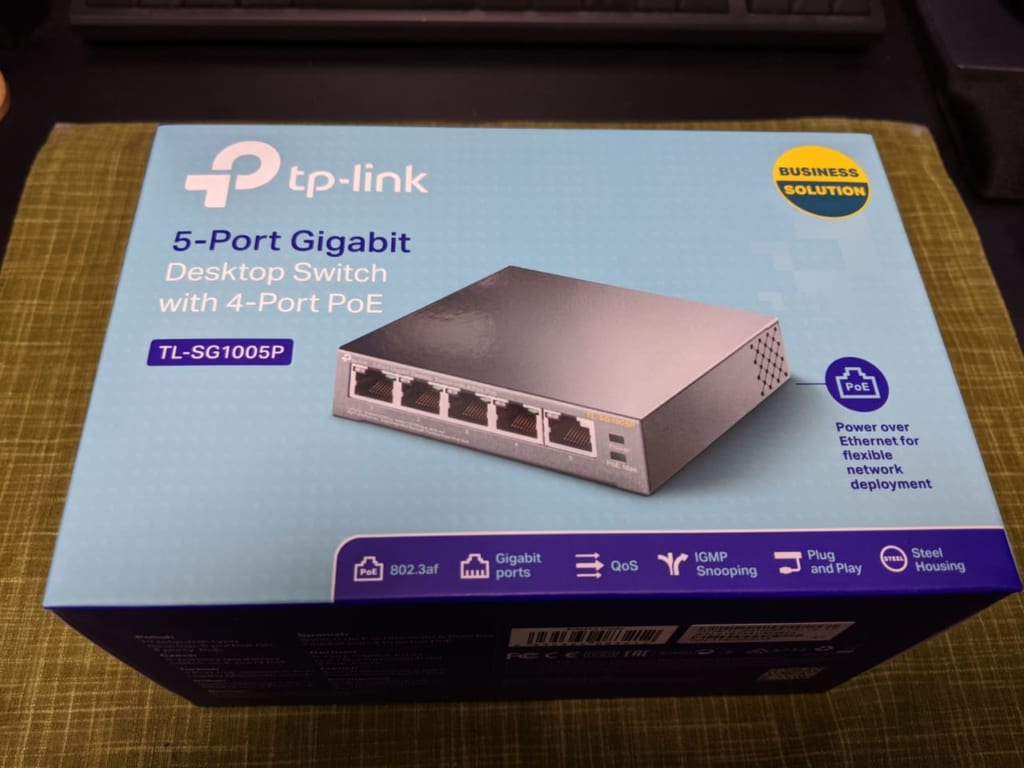
あとは、3DプリンターでPoEスプリッタとRapberry Piを接続するパーツを作成します。
(別途、Raspberry Piの接続用にM2.5 20mmのナイロンスペーサーを使っています。)

こんな感じになりました。
あとは、LANケーブルとLANハブにつなげるだけです。

LANハブとは両面テープでくっつけてあります。LANケーブルもせっかくなので自作しました。(特にPoE対応のLANケーブルでなくても大丈夫でした。)
※作成した3Dプリントデータを掲載しようかと思います。(誰もいらないですかね。。)
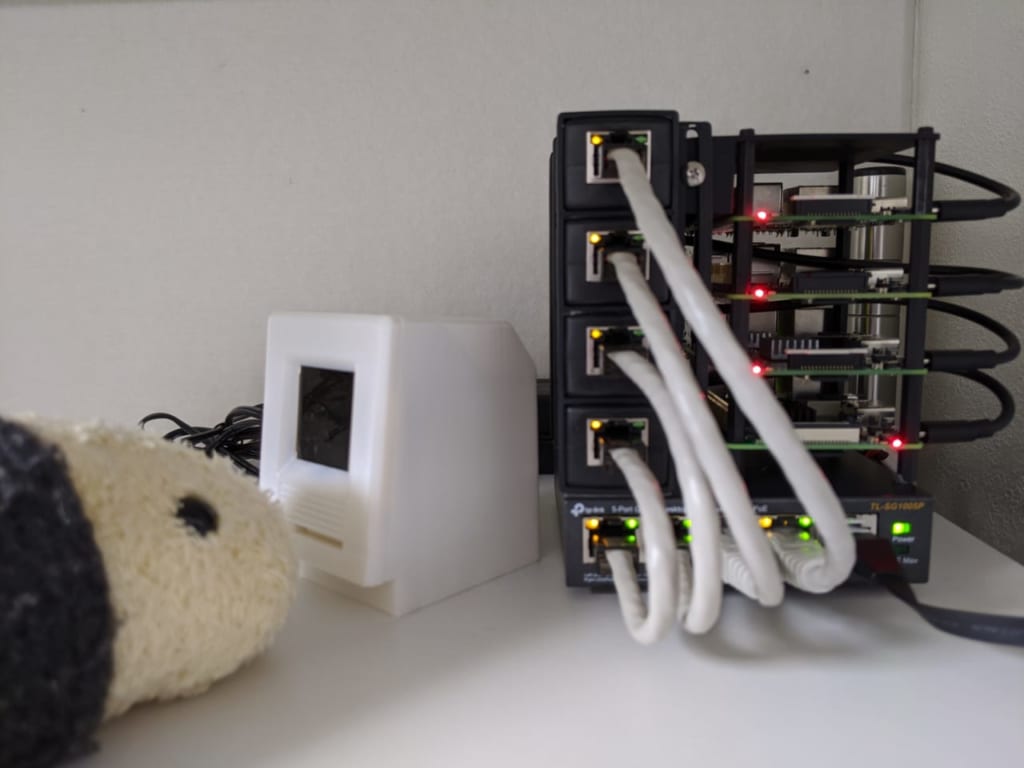
後日、我が家のインフラ担当のカピバラさんがミニサーバールームでメンテナンス中の様子を撮影しました。